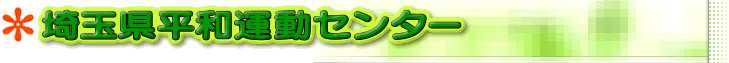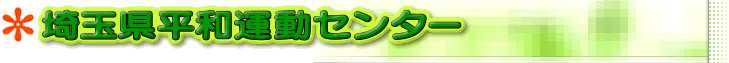川越駅に集合した参加者は、マイクロバスでまず吉見町の吉見百穴に向かいました。吉見百穴は古墳時代の横穴墓として国指定史跡となっていますが、太平洋戦争中は地下軍需工場でした。日本政府は相次ぐ空襲を避けるために重要な軍需工場や軍の施設を地下に移転する計画を進めたのです。吉見百穴下の地下工場はエンジンを製作していた中島飛行機大宮工場を移転する目的で作られました。工事には3千人から3千5百人の朝鮮人労働者が従事しました。私たちは高校生と調査活動に携わってきた大宮北高教諭の江藤善章さんから真っ暗なトンネルを歩きながら説明を受けました。
東松山市の丸木美術館で故丸木位里・俊画伯の大作「原爆の図」などを学芸員の説明を受けながら鑑賞した後、県平和資料館を訪れました。比企丘陵にそびえたつ立派な施設ですが、その展示内容は他県にある平和資料館と比較すると残念ながら見劣りします。ところが上田知事は06年6月の議会で「慰安婦はいたが、従軍慰安婦はいなかった。強制の証拠はない。県平和資料館は自虐史観に流れる部分はないか、世界の平和に対する日本の貢献を伝える役割を充実させるなど、見直すべきである」と発言しました。これを受けて、県平和資料館は同年7月に歴史年表の従軍慰安婦の表記を一方的に変更したほか、南京大虐殺についても「大」を削除し、写真も削除しようとしましたが、各方面からの抗議で写真、キャプション(写真説明)とも復活する動きが起きています。あいにく当日は館側から責任ある説明を受けられませんでしたが、埼玉県平和資料館を考える会の新崎博昭さんからこの間の経過などについて説明を受けました。

丸木美術館「原爆の図」の前で
最後に訪れたのは県平和資料館のすぐ近くにある岩殿観音です。本堂のそばに火災に備えて雨水をためておくための天水桶の台座があります。この天水桶は1842年に比企・入間を中心とした被差別部落の人々によって奉納されたもので、「今後どんな困難が起こってこようとも、そのときには連帯して助け合おう」と誓い合ったといわれています。その翌年には「武州鼻緒騒動」と呼ばれる事件が発生しましたが、誓いを守って比企や入間、遠くは大里から多くの部落の人々が駆けつけました。けれども江戸幕府の厳しい弾圧によって多数の犠牲者を出しただけでなく、天水桶も仁王門の外に放り出されてしまいました。説明にあたった部落解放同盟県連共闘部長の山本道夫さんは、「労働運動もない時代に、一人は万人のために、万人は一人のためにという立場で闘ったことは画期的ではないか」とその意義を語りました。

岩殿観音の天水桶の前で
限られた時間と見学箇所ではありましたが、県内にはこのほかにもたくさんの平和と戦争、人権を考える素材があります。県平和資料館はそれらを集約し、広く県民の目にふれるようにすることこそ任務ではないでしょうか。
|